「ママが良い」「パパが良い」について
最近息子が「パパが良い」となるパターンが増えてきました。
ご飯の時間にお母さんがお隣に座るとスプーンをブンブンして食べないアピールをしたり、
夜は寝室を脱走して、私とお姉ちゃんの寝室に入ってきたり。。。
思えば娘もこれくらいの年齢で「お母さんは嫌い、おっとー大好き」になっていた気がします。
これには「愛着形成」というものが深く関係しているんですが、
あまり馴染みのない言葉(私も保育士試験の勉強で学びました)だと思うので、シェアしたいと思います。
- 子どもに「ママきらい、パパきらい」と言われるようになってしまった方
- まだお喋りできない子どもがいて、将来パパもママも好きになってほしいという方
- 愛着形成期の育児について、実例を知りたい方
そんな方々のお役に立てる記事になっていると思います。
理論的な話と私の実例、両方をお話します
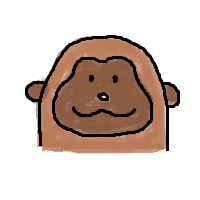
愛着形成とは?
愛着形成とは、特定の人との間に作られる情緒的な結びつきのことを言います。
イギリスのボウルビィ(John Bowlby)という精神分析学・児童精神医学の専門家が提唱した愛着理論に含まれ、
子どもが結ぶ誰かとの信頼関係、とりわけ親との信頼関係の重要性を説くものになります。
子どもが特定の人と愛着形成できることで、それを軸にして、
特定の人以外との関わりを試みたり、徐々に社会に馴染んでいくことができます。
Bowlbyさんによると、愛着形成には4段階あって、それぞれ以下のように重要性が説かれています。
※下記の月齢は目安で、個人差があります
第1段階(誕生~生後12週頃)
周りのすべての人に興味を持ち、手を伸ばしたり、笑いかけたりする。
第2段階(生後12週~6か月頃)
特定の人物に働きかける。対象は授乳などで共に過ごす時間が長い母親であることが多い。
この時期の子は、特定の人(例えば母親)、とそれ以外の人(例えば父親・兄弟など)を区別する。
第3段階(生後6か月~3歳頃)
大好きな人、そうでない人の区別がついてくる。
お腹を満たしてくれる、オムツを交換してくれる、いつも遊んでくれる、など経験の積み重ねにより、
いつも世話をしてくれる人と、それ以外の人を区別する。(特定の人が居ないと不安になる)
第4段階(3歳頃~)
大好きな人との絆が確固たるものになり、一定時間見えなくても戻ってくることが理解できる。
これにより、自分から社会に興味を持ち、歩んでいくことができるようになる。
(第3段階までの土台が、特定の人以外と愛着形成をする上で大切)
私の子どもたちの場合はどうか
息子が生まれる前は、家事分担は無くて、全ての家事を私が担っていました。
すなわち、上記の第3段階で、身の回りのお世話は「父親」もしくは「保育士さん」がやってくれるものと経験し、
卒乳以降、娘は母親から父親に愛着の対象を変化させ、だいぶ早い時期に「おっとー大好き!」になりました。
これは悪循環に陥りやすくて、「お母さんやだ」と言われると妻の方も拗ねてしまい、
保育園の送り迎えで手を繋がない→転んでケガをする→お母さんに怒られる→お家でお父さんに手当してもらう
という愛着形成を悪化させる残念なパターンに入ることもしばしばありました。
そんなときにもう少し娘の身の回りの世話をしようと、妻に働きかけたとき、言われたのが次の台詞。
「私は食料品の宅配頼んだり、服を買ったりしてる。仕事してるんだからそれ以上はムリ。」
うーん…それだと娘に愛情が伝わらないのよ。。。お金じゃなくて食べさせたり、着替えさせたりすることが大事。
以前とある保育士さんがYouTubeの中で、子育ては「質」より「量」なんです!と発信していて
確かに、どれだけ深い愛情を込めて美味しいごちそうを1回提供するよりも、
日常的にご飯を用意して食べさせる方が、愛着形成に効果的というのはスッと理解できるような気がしました。
今の娘は、徐々に他人の心の存在を理解しているのか、妻に対する直接的なヒドい台詞は控えるようになりました。
それでもやっぱり「おっとー!おっとー!」と頼る対象が偏っている状況を見ていると、
(良くも悪くも)幼少期に築いた愛着関係というのはなかなか崩れないものだなぁと思います。
こちらに関しては以前「心の理論」についてご説明した下記の記事をご覧ください。

前述の愛着形成段階で言えば、私の息子は第3段階にいます。
授乳は妻がやっていましたので、第2段階では「母親」と信頼関係が結べ、お母さん大好きという感じでした。
ところが冒頭で触れたとおり、最近愛着の対象が「母親」から「父親」にすり替わって来ているように思うのです。
今まさに愛着形成期、この間にどれだけ愛情を注げるか?がポイントになってくると考えています。
育休明けからは食事の支度を妻と半々で分担するようになり、多少改善したかなとは思いつつも、
いわゆる「名もなき家事」というやつは私の担当であり、子どもと一緒に遊んだり、
食事を食べさせたり、トイレのお世話をしたり、と言う日々の積み重ねは偏ってるんですよね…。
再びあの悪循環には陥らせたくないなぁ、と思うのですが、どうしたものか…。(息子も妻も嬉しくないハズ…)
1人と愛着形成を結べていれば良いのでは?という意見もあるとは思いますが、
私はあまりこれを良い状態とは思っていないです。
なぜなら成長する過程でいずれ子どもたちは「反抗期」を迎え、親へももちろん反抗します。
そんな中、例えば娘が私を「臭い!汚い!近寄らないで!」と言うようになったとき、(´;ω;`)ブワッ
家で他に頼れる人が居なかったらツラいし、変な方向に行ってしまうのではないかと心配しています。
心の支えが両親分の2本あれば、姉弟も含め、家の中に頼る選択肢が3つある状態になるわけです。
1人と深い絆で結ばれていても、それが壊れたら家の中に居場所がないとか、それは避けさせてあげたい。
だからこそ、パートナー同士が協力していくことが大事だと思うんです。
が、これがなかなかうまく行かないというジレンマ…

ただ一つだけ、私も気を付けているのですが、
パートナーの悪口を子どもに言うのだけは止めた方が良いです。(つい言いたくなるけどね…)
味方を増やそうとしているのかもしれないですが、それは視野が狭い。子どもの将来頼る選択肢を減らす行為です。
- 子どもの成長において、愛着形成期はとても大事
- 特に第3段階で「いつも世話をしてくれる人」認定されることは、強固な信頼関係の土台
- 家庭の中に、信頼の柱をいくつも用意して冗長化してあげよう
今回はボウルビィ(John Bowlby)さんの愛着理論をベースに、
私の家庭での2つの例を挙げながら、これからどう育児をしていくかを改めて考えてみました。
この記事が子育てに関わる方のお役に立てていれば嬉しいです。
最後までお読み頂きありがとうございました!

