子どもとの「しりとり」が楽しくなるコツ
娘は保育園の行き帰り、「しりとり」をするのが大好きです。
私も娘がどんな言葉を身につけたのか、びっくりしながら知ることができるので、なかなか好きです。
また子どもが分かる単語縛りでやるしりとりは良い頭の体操になります。
- 子どもとのしりとりを楽しむコツを知りたい方
- 平凡な遊びをワンランクアップする工夫のヒントを得たい方
- しりとり=ただの暇つぶしになってしまっている方
そんな方々が気づきを得られる記事になっています。
それでは、行ってみましょうー!
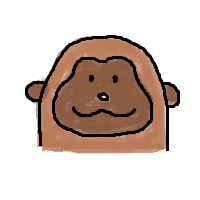
子どもとのしりとりで考えていること
皆さんのお子さんが好きなことってありますか?
私の娘はコロコロ趣味が変わるんですが、今はディズニープリンセスと、マインクラフトが好きです。
なので、しりとりのときも「アリエル」「ラプンツェル」(難しい「る」に繋がるけど…)とか
「魔女」「ドレス」、マイクラなら「ピッケル」「ラピスラズリ」とかに繋げると盛り上がります。
子どもの中では、大好きなあの言葉につなげたい…と思うことがあるようで、
「ら」で始まる言葉が良いなぁ…と言ったりするので、繋げてあげると「待ってました!」とばかりに
「ラプンツェル!」と1番お気に入りのプリンセスの名前を教えてくれます。
普段から子どもの趣味を一緒に楽しんでいることが大切◎
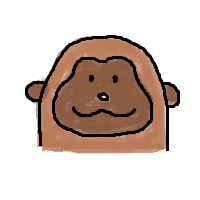
あとは、ちょっとズルかもしれないですが、「形容詞」+「名詞」でアレンジするのも楽しいです。
例えば「パリパリおせんべい」「ひんやりアイス」「ふわふわうさぎ」などです。
定番の食べ物や動物も、ちょっとアレンジするだけで、想像しやすくなりませんか?
娘が「かき氷」と言ったときには「何のシロップがかかっているの?」と聞いてみて
「ピンクのいちごかき氷だよ!」「美味しそう!ひんやりかき氷食べたいねぇ」と
ちょっと雑談を挟んだりするのも楽しいです。
五感に伝わるようなものだと、想像しやすいね!
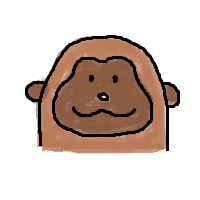
しりとりは、ほぼ負けることは無いと思うのですが、あまりに「る」が続くと辛くなったりしませんか?
同じ言葉を繋げ続ける…みたいな勝つための戦法は、子どもが小さいうちは避けた方が良いかもです。
もう思いつかないからや〜めた!つまんない!となったら、せっかくの楽しみが台無しです。
小さい子どもはまだ「勝ち負け」との付き合い方がよく分かっていない部分があります。
もちろん勝つ人がいれば、負ける人もいる、と言うことを教えると言うのも成長という面では大事ですが、
それを「しりとり」にまで持ち込む必要はないかな、と考えています。
勝負の世界は、努力で結果を左右できる場合に教えれば良い、というのが持論です。
なので、私は基本的に娯楽では子どもを勝たせる、或いは引き分けになるよう調整します。
そうして「いろんな言葉知ってるんだね!」とか「最後まで頑張ったね!」とか
勝負の結果では無いところで、良いなと思った所をコメントし、自己肯定感が上がれば良いなと思っています。
- 子どもの好きな単語を選ぼう!
- ちょっと想像したくなる工夫をしよう!
- 続けやすいように大人が調整してあげよう!
ちょっとした工夫で、平凡な遊びであるしりとりも、楽しさも有用性もワンランクアップします。
道具なしで遊べる「しりとり」は、移動中など重宝しますよね。
まだ「アー」と「ウー」しか言えない息子としりとりする日が私は楽しみです。
ただの「暇つぶし」から「想像力膨らむ楽しい時間」に変えてみよう!
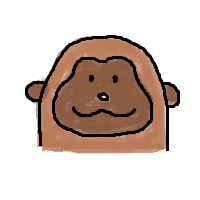
最後までお読み頂き、ありがとうございました!

